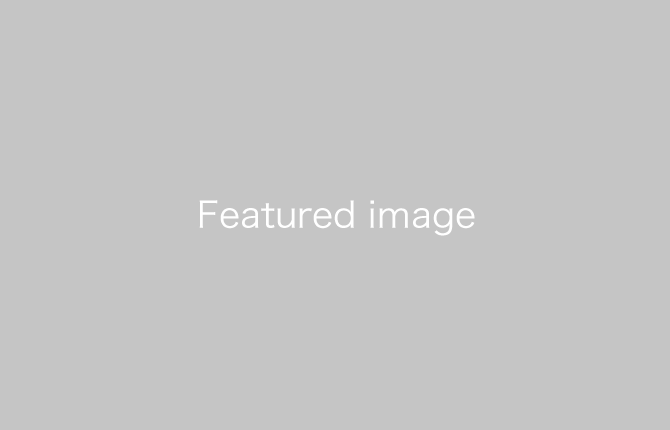適応障害で復職後にしんどいと思う理由
適応障害で復職後に感じるしんどさには、次の3つが関係します。
- 業務量や責任が重すぎる
- 周囲との人間関係に不安を感じる
- 憂うつや不眠などの症状により仕事に支障がでる
復職して業務量や責任が休職前と同じだと、まだ回復しきれていない心身には負担が大きすぎます。以前と同じペースで仕事を進めようとすると、過度なストレスを感じてしまうのです。
また、周囲との人間関係に不安を感じることも要因となります。自分の状態を理解してもらえるかという不安があるため、同僚との関係を再構築することが精神的な負担となるのです。
さらに、憂うつや不眠などの症状が、仕事に支障をきたすこともあります。[1]適応障害の症状は目に見えにくいため、周囲に理解されにくいという難しさもあります。その結果、集中力の低下や体調の変動が起こり、業務に集中できなくなるのです。
適応障害で仕事がしんどいときの対処法
適応障害で仕事がしんどいときの対処法には、次の5つがあります。
- 無理をせずに休む
- 業務量を見直してもらう
- タスクの優先順位を見直す
- 職場の人とランチを食べる
- リラックスできる時間をつくる
仕事へのモチベーションを維持するために、ぜひ実践してみてください。
無理をせずに休む
体調が悪かったり集中力が下がったりしたら、無理をせずに休むことが大切です。
適応障害から復職した後は、焦らず自分のペースで仕事を進めましょう。休息は回復するために必須であり「自分が弱いからなんだ」と考える必要はありません。病院と相談しながら、適切な休養のタイミングや方法を検討してみてください。
自分の心身の状態を受け止め、必要に応じて短時間勤務や在宅勤務などの柔軟な働き方を提案することも有効な対処法です。
業務量を見直してもらう
適応障害による負担を軽くするためには、業務量の調整をしましょう。
上司や人事と話し、業務内容について提案をしてみてください。たとえば「今はこの業務に集中したいので、他の業務の優先度を下げてほしい」といった希望を具体的に伝えます。正直に現状を説明することで、あなたにとって適切な業務量と内容に調整してもらえるでしょう。
とくに、重要な案件はチームで対応する体制を整えることで、個人の負担を減らせます。ひとりで抱え込まずに、周囲の協力を得ながら進めるようにしてみてください。
タスクの優先順位を見直す
適応障害の症状によって集中力が続かないときには、タスク管理が重要です。
優先順位を明確にし視覚的に整理することで、心理的な負担を減らせます。たとえば、スマホやパソコン、手書きのメモなどを活用してみましょう。タスクを色分けしたり難易度や緊急度で分類したりすると、より整理しやすくなります。
また、1日の最初に重要タスクを決めて取り組み、小さな成功体験を積み重ねると自信を取り戻しやすくなります。柔軟な考え方と計画的な取り組みが、適応障害からの職場復帰をスムーズに進めるのに役立つのです。
職場の人とランチを食べる
適応障害からの復職後は、職場の人と一緒にお昼を食べてみてください。
ランチタイムは、同僚とコミュニケーションを深める絶好の機会です。職場の雰囲気から離れリラックスした状況で会話することで、お互いをより深く理解できます。信頼できる同僚と話すと、しんどさを軽くできるでしょう。
ムリに大人数で過ごす必要はありません。まずは、話しやすい同僚1人とランチに行ってみてください。気軽に話せる関係を築けば、徐々に職場に馴染めるようになります。
リラックスできる時間をつくる
適応障害から復職するときは、リラックスできる時間をつくりましょう。
心身の健康を維持するためには、自分に合うリラックス方法を見つけ日常的に実践することが大切です。瞑想やヨガ、ストレッチは、心身をリラックスさせるのに有効です。好きな音楽を聴いたり読書をしたりなど、趣味に没頭してみてください。
また、仕事とプライベートのバランスを保つことも大切です。仕事が終わったら切り替えて、自分の時間を楽しむようにしてください。心身のエネルギーを回復させることが、復職後の生活をスムーズに送るポイントとなります。
適応障害で復職後のしんどさを乗り越えるための働き方
適応障害からの復職は、あなたに合った柔軟な働き方が鍵となります。
- 短時間勤務
- リモートワーク
- フレックスタイム制
さまざまな働き方を活用することで、心身の負担を軽くし職場に徐々に適応できるようになります。会社と協力しながら、最適な方法を見つけていきましょう。
短時間勤務
短時間勤務は、適応障害からの復職に効果的な働き方のひとつです。フルタイムで働くのが難しい人や決まった時間だけ働きたい人が、勤務時間や日数を短くして働ける制度です。
たとえば、1日4時間から始め、徐々に勤務時間を増やしていきましょう。ムリなく業務をこなしながら、段階的な労働時間の調整ができます。
復職と同時にフルタイム勤務に戻すのではなく、短時間正社員制度を活用して再発を防ぐことでスムーズに職場復帰を進められるのです。
リモートワーク
リモートワークは、適応障害からの復職を効果的に支援する働き方です。リモートワークとは、所属するオフィスに出勤せずに自宅を就業場所とする勤務形態です。
自宅では周囲を気にせず、自分のペースで業務を行えます。たとえば、好きな音楽を聴きながら作業したり、休憩時間にはリラックスして過ごしたりすることができるのです。 さらに、リモートワークは柔軟な勤務時間を可能にするため、通院やリハビリなどの治療と両立しやすく、ワークライフバランスの向上にも貢献します。
適応障害からの復職において、心身の健康を維持しながらスムーズに職場復帰を果たすためには、リモートワークは有効な選択肢となるのです。
フレックスタイム制
適応障害からの復職において、フレックスタイム制は柔軟性の高い働き方です。
一定の期間における労働時間の合計があらかじめ定められており、その範囲内で日々の始業・終業時刻や労働時間を自分で決められます。たとえば、朝早く出社して午後に退社したり、逆に遅く出社して夜まで働いたり、自分の都合に合わせて柔軟に働けます。通院やリハビリなどの時間を確保しやすくなり、仕事と生活のバランスを取りながら、効率的に仕事を進められるのです。
適応障害から復職した人にとって、自分の心身の状態に合わせて勤務時間を調整できることは大きな助けとなります。都合に合わせて時間を自由に配分できるため、心身の負担を減らしながら職場復帰を実現できるのです。